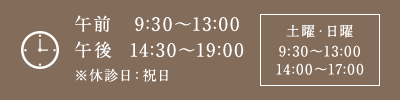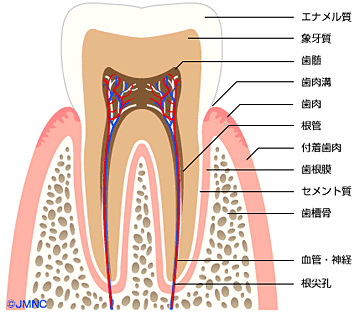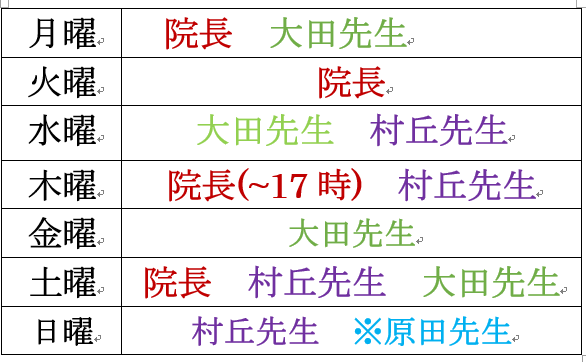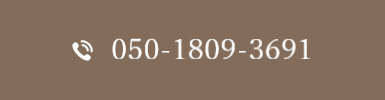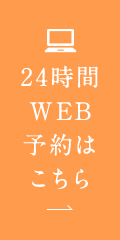2019.04.04
こんにちは!
今日はお悩みの方が多い親知らずについてお話したいと思います☺
親知らずを抜いたほうがいいのはこんな場合
①親知らずが少しだけ見えていて、これ以上生える見込みがない
親知らずが斜めになっていたり、横に倒れている場合はきちんと生え切らず、虫歯や歯周病を起こすことは免れません。
②親知らずが手前の歯を強く押していて歯並びに影響を与えている
親知らずが手前の歯を強い力で押して、歯並びが悪くなってしまうことがあります。
③親知らずの周りに嚢胞ができている
レントゲン上で埋もれた親知らずの周りに袋状の影が見えることがあります。この袋状の物を嚢胞と呼びますが、残しておくことでトラブルを起こす原因となります。
④親知らずがかみ合わずに歯ぐきや頬の粘膜を傷つけている
親知らずはかみ合わなければどんどん延びていきます。そうすると向かいの歯ぐきや頬の粘膜を噛むようになり、痛みを引き起こします。また顎関節症を起こす原因にもなりえます。
⑤親知らずがひどい虫歯や歯周病になっている
親知らずは歯ブラシが届きにくく、虫歯や歯周病が進みやすい歯です。きちんと生えている場合でもひどい虫歯や重度の歯周病になっている場合には残しておかないほうが良いでしょう。
「親知らずの抜歯は痛い」というイメージが根強くあるようです。しかし、実際は抜歯の際には麻酔が効いていますので痛みを感じることはほとんどありません。当院では麻酔自体も痛みを感じさせない工夫をしておりますのでご安心ください♪
痛みを感じるというのは通常、麻酔が切れてからのことです。
傷口ですから痛むのは仕方のないことなのですが、痛みを感じる前に痛みを飲んでいただくなどすることで、術後の痛みも極力抑えることが可能です。
親知らずを抜くと小顔になる、とちまたで耳にすることがあります。あながち間違いでもありません。その理由を挙げてみます。
①親知らずの周囲の骨が痩せる
下の親知らずの場合、エラに近い場所に位置していますので、抜歯することで骨が吸収してエラの部分が若干ほっそりする可能性があります。
②顎の筋肉が痩せる
しっかり噛んでいる親知らずを抜いた場合、その部分が噛まなくなることにより筋肉が使われなくなるため、筋肉が痩せてきます。また、噛み合っていない場合でも、親知らずが手前の歯を押していたりする場合に歯並びがずれたり、違和感を感じることによって無意識にかみしめたり歯ぎしりをすることがあります。その場合もその原因となっている親知らずを抜くことでかみしめ、歯ぎしりなどがなくなり、筋肉がすっきりしてくることが考えられます。
親知らずの抜歯でお悩みの方はぜひ一度ご来院ください(^^)/