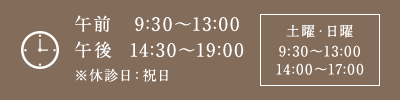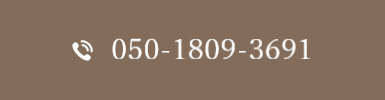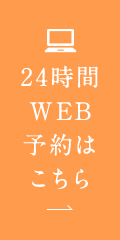歯医者には歯が痛くなってから行くという考え方から、虫歯や歯周病などの口腔内の病気を予防することを目的とした予防として歯科へ通院するという考え方が少しずつ浸透しつつありますが、2024年のあるデータでは予防歯科で通うという人の割合は約3割にとどまっているそうです。
ここでは予防歯科の大切さと予防歯科に欠かせない定期検診についてお伝えしたいと思います。

予防歯科の大切さ
予防歯科とは虫歯や歯周病などの口腔内の病気をなる前に予防、または早期に発見、治療して健康な歯と口腔内環境を保つという考え方です。歯を削ったり抜歯したりする「治療」よりも健康な歯を維持する「予防」に重点を置くことで生涯にわたり自分の歯を守ることが目的です。
予防歯科には自宅で行うセルフケアと歯医者で行うケア(定期検診)と2つあります。セルフケアも大切ですがセルフケアだけだと、どうしても自分では磨けないところも多く磨き残しが歯石になり細菌が繁殖することで虫歯になるケースが多いです。
では歯科で行う定期検診の内容について年齢別にみていきたいと思います。
年齢別定期検診の内容
よく何歳から歯科検診が必要でしょうか?と問い合わせと受けることがあります。乳歯は生後6か月頃から生え始めるため歯が生え始めたこのことから歯科医院で口腔内のチェックなどの定期検診を受診することが推奨されています。
生後6か月頃
乳歯が萌出し始めるためこの時期から生えはじめの歯の向きや、汚れやすい部分を早期に把握し、ブラッシング指導やフッ素塗布など予防ケアをスタートできます。

1歳前後(1歳6か月児健診)
多くの自治体では「1歳6か月児健診」に歯科検診が組み込まれており、ここをお子さんの初回受診の目安にされるケースが多数です。1歳を過ぎると上下の乳歯が揃い、お口の発育状態や噛み合わせチェックも行いやすくなります。
以降は、歯石やバイオフィルムの再付着を防ぐためにも 3〜6か月に1回 を目安に定期検診(クリーニング+チェック)を続けると、むし歯・歯周病の予防効果が高まります。ご家族の生活リズムやリスクに応じて、かかりつけ歯科医師と相談しながら最適な間隔を決めていきましょう。歯医者での定期検診は、年齢によって重点が変わっていきます。以下に、年齢ごとの主な検診内容の違いやチェックされるポイントをまとめてみました。
0〜6歳(乳児・幼児)
目的:虫歯予防・噛み合わせの確認・口腔習慣の指導
乳歯の萌出状況の確認
虫歯の有無(特に上の前歯)
フッ素塗布
歯磨き指導(親へのアドバイス含む)
指しゃぶりや口呼吸などの癖のチェック
7〜12歳(小学生)
目的:永久歯への生え変わり確認・虫歯&歯並びチェック
永久歯の萌出状況
虫歯・歯肉炎のチェック(この時期に虫歯や歯周病が増え始めます)
歯列・噛み合わせの異常チェック(矯正が必要かどうか)
正しいブラッシング指導
食生活や間食指導

13〜19歳(中高生)
目的:歯肉炎・歯列不正・生活習慣病の芽をチェック
思春期性歯肉炎の有無
歯列や顎の発育状況
磨き残しのチェック&改善指導
部活動や受験でのストレスによる食いしばり・歯ぎしりの確認
20〜39歳(若年・成人)
目的:歯周病・虫歯予防&セルフケアの継続支援
初期の歯周病(歯肉炎・歯周炎)の検査
歯石の除去(スケーリング)
虫歯の早期発見
噛み合わせや詰め物・被せ物のチェック
妊娠・出産予定がある人へのマタニティ歯科指導

40〜64歳(中年)
目的:歯周病の進行予防・全身疾患との関連チェック
歯周ポケットの測定(歯周病の進行度確認)
動揺歯(グラついている歯)のチェック
咬合バランス(噛み合わせ)の確認
歯の喪失予防・ブリッジや義歯の調整
糖尿病・高血圧など全身疾患との関連の相談
65歳以上(高齢者)
目的:残存歯の維持・誤嚥予防・咀嚼機能の維持
義歯の適合チェック
嚥下機能(飲み込み)のチェック
舌や頬の動き、口腔乾燥の確認
転倒や病気によるセルフケア困難に対応した指導
定期的な口腔ケア支援(介護予防の一環)
必要に応じて、レントゲン撮影やデンタル撮影、口腔内写真などが年齢問わず行われます。
]
終わりに
歯の定期検診は、なるべく早い段階から「かかりつけ」を持つのが望ましいとされています。何歳であっても 「自分に合った予防とケア」 を続けることが一番大切です。虫歯になったり、痛みが出る前に定期的に歯科の検診を受け、健康な歯を保てるよう予防歯科は大切です。是非歯科に最近通っていない等あるようでしたら歯が痛くなくても定期検診についてお気軽にご相談ください🌻